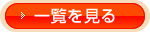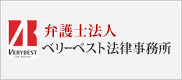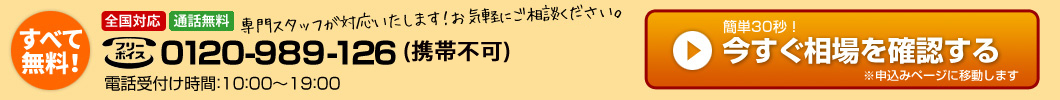鈴木良太【編集者・外壁塗装110番代表】
鈴木良太【編集者・外壁塗装110番代表】幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。
外壁・屋根塗装だけで雨漏りは直らない?雨漏りの原因・予防・応急処置
雨漏りしてきたから外壁塗装や屋根塗装することで補修しようと考える人も多いと思います。
結論から言うと、外壁塗装や屋根塗装だけで雨漏りは直りません。
なぜなら、雨漏りの原因は、塗装面の劣化以外が多いからです。
例えば、
・新築時の手抜き工事
・屋根にあるトップライトの周辺の劣化
・サッシのパッキンの劣化
・太陽光の設置で屋根に穴をあけた箇所の劣化
・雨樋のつまり
などです。
そのため、雨漏りを完璧に直すためには、塗装よりももっと根本的な補修が必要になります。
この記事では、雨漏りが起きやすい箇所とそれぞれの原因についてご説明します。
記事を読み終わる頃には、雨漏りの怖さと気をつけるべき点が明確にイメージできていることでしょう。
雨漏りは雨水が天井から滴り落ちる状態だけではない
部屋の天井から雨水がポタポタと滴り落ちるのを「雨漏り」だと思っている人も多いでしょう。
結論から言うと、雨漏りは雨水が天井から滴り落ちる状態だけを指していません。
なぜなら、雨漏りとは「雨水が意図せぬところから建物の内部に浸入する現象」すべてに当てはまるためですね。
辞書によっては「雨水が屋根の穴を通って、天井などから滴り落ちる」と書いてありますが、そこまでになると被害はかなり進んでいる状況です。
雨漏りが起きやすい箇所と原因
雨漏りが起こりやすい箇所としては「屋根」「ベランダ」「雨樋」「外壁」「窓」があげられます。
この章では、それぞれの箇所ごとの雨漏りの主な原因についてご説明します。
屋根にできた穴や隙間から雨水が侵入
屋根にできた穴や隙間から雨水が侵入してくることで雨漏りが発生します。
屋根に穴や隙間ができる主な原因をご紹介します。
日本瓦のズレや割れ
 日本瓦のズレや割れは、昔ながらの土葺き工法の屋根で見られる現象です。
日本瓦のズレや割れは、昔ながらの土葺き工法の屋根で見られる現象です。
瓦の下にある葺き土が経年劣化で痩せたり、地震などで屋根が大きく揺れた場合に起こります。
日本瓦本体は、非常に丈夫なので滅多に割れることはありませんが、台風や暴風で何かが落下してきた場合は、割れてしまうこともあります。
スレートの浮き、反り、割れ
 スレートの浮き、反り、割れは、スレートが温度変化や紫外線、風雨などの影響で劣化すると発生します。
スレートの浮き、反り、割れは、スレートが温度変化や紫外線、風雨などの影響で劣化すると発生します。
漆喰、コーキングの剥がれ
 屋根と瓦の間を埋める漆喰や、スレート屋根の隙間を塞ぐコーキングが劣化や施工不備によって剥がれてしまうことがあります。
屋根と瓦の間を埋める漆喰や、スレート屋根の隙間を塞ぐコーキングが劣化や施工不備によって剥がれてしまうことがあります。
金属系屋根の錆
 トタンやガルバリウムなどの金属系屋根の錆は、防水塗装の剥がれや加工断面の防水不備などが原因で発生し、錆びると穴が開いて雨水が浸入します。
トタンやガルバリウムなどの金属系屋根の錆は、防水塗装の剥がれや加工断面の防水不備などが原因で発生し、錆びると穴が開いて雨水が浸入します。
棟板金の釘浮き
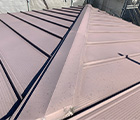 棟板金とは屋根の頂点に被せてある山型の金属板のことです。
棟板金とは屋根の頂点に被せてある山型の金属板のことです。
棟板金の釘浮きは、棟板金をとめる釘の劣化や強風によって起こり、浮いた隙間から雨水が浸入してしまいます。
トップライト周りのコーキング
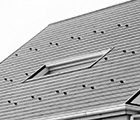 トップライト周りのコーキングは、常に雨や太陽光を浴びる箇所なので劣化が早く、普段から屋根に登って劣化を確認する人は少ないので、雨漏りの原因になりやすい箇所です。
トップライト周りのコーキングは、常に雨や太陽光を浴びる箇所なので劣化が早く、普段から屋根に登って劣化を確認する人は少ないので、雨漏りの原因になりやすい箇所です。
太陽光を設置するときにあける穴
 太陽光を設置する場合は、屋根に穴をあけて取り付けます。
太陽光を設置する場合は、屋根に穴をあけて取り付けます。
そのため、太陽光を設置するときにあける穴の位置が不適切だったり、穴を埋める箇所の劣化が原因で雨漏りすることがあります。
太陽光は、助成金制度が始まった時期にいきなり注目を浴び技術力がない業者も取り付けていたので、施工ミスが多かったと言われいています。
外壁にできた隙間から雨水が侵入
外壁にできた隙間から雨水が侵入することで雨漏りが発生します。
外壁に隙間ができる原因についてご紹介します。
モルタル、漆喰、コンクリートのひび割れ
 モルタル、漆喰、コンクリートのひび割れは、外壁材の乾燥による収縮や地震などが原因で発生し、ひび割れた部分が雨水の浸入口になります。
モルタル、漆喰、コンクリートのひび割れは、外壁材の乾燥による収縮や地震などが原因で発生し、ひび割れた部分が雨水の浸入口になります。
外壁のコーキング劣化
 サイディングボードやタイルの隙間を埋めているコーキング材は、劣化してくると痩せて崩れやすくなります。
サイディングボードやタイルの隙間を埋めているコーキング材は、劣化してくると痩せて崩れやすくなります。
そのため、外壁のコーキングが劣化して埋められていた隙間が出てくると、雨水が浸入します。
ベランダの経年劣化や施工ミスが原因で雨水が侵入
ベランダの経年劣化や施工不良が原因で雨水が侵入し、雨漏りが発生してしまいます。
ベランダの経年劣化や施工ミスなどによって起こる症状についてご紹介します。
排水口の詰まり
 排水口の詰まりは、枯葉などのゴミが溜まっていることが理由で発生します。
排水口の詰まりは、枯葉などのゴミが溜まっていることが理由で発生します。
詰まった状態で放置していると、雨水の流水経路が塞がれて水が溢れ出し、溢れ出した水は外壁などの小さな隙間から室内へ浸入していきます。
床のヒビ割れ
 床のヒビ割れは、防水塗装の剥がれや経年劣化によって起こり、ひび割れた部分から雨水が浸入してしまいます。
床のヒビ割れは、防水塗装の剥がれや経年劣化によって起こり、ひび割れた部分から雨水が浸入してしまいます。
取り合いの隙間
 取り合いの隙間とは、ベランダの床と壁の接続部分に隙間が発生している状態で、コーキングの劣化や施工ミスにより隙間ができると雨水が浸入する原因になります。
取り合いの隙間とは、ベランダの床と壁の接続部分に隙間が発生している状態で、コーキングの劣化や施工ミスにより隙間ができると雨水が浸入する原因になります。
手すりのサビ
 手すりのサビや塗装の剥がれからできた穴があくと、そこに雨水が入っていきます。
手すりのサビや塗装の剥がれからできた穴があくと、そこに雨水が入っていきます。
家屋は想定外のルートからの浸入に意外に弱く、壁を伝って室内に浸透してしまうことがあります。
雨樋の流水経路に不具合があり雨水が侵入
雨樋の流水経路に不具合があると雨水が正しく排水されず、溜まった雨水が侵入して雨漏りに繋がります。
雨樋に生じる不具合についてご紹介します。
雨樋の詰まり
 雨樋はベランダの排水口と同様にゴミが溜まりやすい場所なので、雨樋の詰まりが起こると雨水が浸入してしまいます。
雨樋はベランダの排水口と同様にゴミが溜まりやすい場所なので、雨樋の詰まりが起こると雨水が浸入してしまいます。
雨樋の傾きや歪み
 雨樋は適正な勾配をもって設置されていなければ、有効に機能することが出来ません。
雨樋は適正な勾配をもって設置されていなければ、有効に機能することが出来ません。
自然災害などにより雨樋に想定外の負荷がかかり傾きや歪みが発生すると、適正な流水経路が確保できず雨漏りにつながります。
窓枠周辺の経年劣化によって雨水が侵入
窓枠周辺の経年劣化によって雨水が侵入すると雨漏りが発生してしまいます。
通常、窓は軒があるので普通の雨であれば、軒に守られて雨に直接さらされることはありません。
横風を伴うような強い雨が降ったような場合にだけ、雨が染み出してくるのが窓からの雨漏りの特徴です。
窓枠周辺で起こる経年劣化の症状についてご紹介します。
窓枠のコーキング劣化
 窓枠はコーキングによって外壁との隙間が埋められていますので、窓枠のコーキングが劣化して隙間ができると雨水が入りやすくなります。
窓枠はコーキングによって外壁との隙間が埋められていますので、窓枠のコーキングが劣化して隙間ができると雨水が入りやすくなります。
窓枠周辺の外壁の劣化
 窓枠の四隅の外壁は構造上弱い部分なので窓枠周辺の外壁は劣化しやすく、地震の揺れなどで亀裂が入ってしまいます。
窓枠の四隅の外壁は構造上弱い部分なので窓枠周辺の外壁は劣化しやすく、地震の揺れなどで亀裂が入ってしまいます。
雨漏りの予防と応急処置
屋根や外壁は、建ててから10年も経つと、経年劣化や震災などによって雨漏りが生じることがあります。
被害が拡大する前に、定期的にチェックして前兆をとらえられれば、早めのメンテンスが可能で、費用も最小限に抑えられます。
この章では、自分でできる雨漏りのチェックポイントや、補修が高額になる可能性がある二次被害について説明しています。
雨漏り予防に半年から一年に一度はチェック
雨漏り予防に半年から1年の間に一度のペースで定期的にチェックしましょう。
なぜなら、建物は常に紫外線や雨風の影響を受け、日々劣化が進行しているからです。
また、台風や地震などの自然災害で建材が破損して雨漏りに繋がるケースもあるので、定期的にチェックして早期に発見することが大切です。
特に雨や雪が多い地域では、自宅の様々な場所を点検しましょう。
雨や雪は建物を劣化させる要因となり、さらに雨や雪自体が内部に入り込んできてしまいます。
以下、雨漏り対策で必要なチェックポイントを10個ご紹介します。
10個の雨漏りチェックポイント
□屋根の瓦がずれていないか
□瓦と瓦のあいだに隙間やひびや抜けた釘がないか
□金属製の屋根にサビはないか
□天窓付近に劣化はないか
□外壁にひび割れがないか、変色していないか
□雨樋やベランダの排水口にゴミや落ち葉が詰まっていないか
□ベランダの床にひびはないか
□天井や壁、窓枠にシミやカビがないか
□天井や壁のクロスが浮いていないか
□室内外のコーキング部分が劣化していないか
もし自分でチェックしていて雨漏りが疑われたら、応急処置をしてすぐに専門業者に相談してください。
業者に依頼したほうが安全
屋根に登るのに慣れていない方は業者に依頼したほうが安全です。
なぜなら、素人が屋根に登るのは転落事故を招く危険な行為となるためですね。
雨漏りの修繕は豊富な知識と技術が必要となるので、専門の業者に相談をして直接建物を調べてもらいましょう。
調査費用は調査方法や業者によって異なり無料~数万円程度です。
雨漏りしてきた場合、すぐできる応急処置
万が一、雨漏りしてきた場合の処置方法をご紹介します。
浸水箇所にバケツや雑巾などを用いて水が広がらないようにする
浸水箇所にバケツや雑巾などを用いて水が広がらないようにしましょう。
室内に水が広がると床下や柱などの木材を濡らし、腐食やシロアリが発生する原因になってしまいます。
シロアリは湿った木材を好み食べるため、建物を支える木材までも食べられ耐震性を脅かします。
バケツを使用するときは、バケツの下に新聞紙やレジャーシートなどを敷いて床が濡れるのを防ぎ、水が飛び散らないようにバケツの中に新聞紙やタオルを入れておくと良いでしょう。
吸水シートで水を吸い取る
バケツや雑巾で拭くだけでは被害を抑えられない場合は、吸水シートで水を吸い取りましょう。
吸水シートは、約400gのシート1枚で500mlのペットボトル20本分の水を5~10分程で吸い取ることができるため、雑巾で拭いても対応しきれない時に便利なアイテムです。
水が侵入しているサッシ周りや天井裏などに敷き詰めて吸水したり、バケツの中に入れて水の飛び散りを防ぐ際に役立ちます。
吸水シートは10枚入りの場合、1,000円~2,000円程度で購入可能で、商品によっては使用後に3週間程自然乾燥させることで再利用できるものもあります。
防水テープやコーキング材を原因箇所に塗布
防水テープやコーキング材を購入し、原因と思われる箇所に塗布しましょう。
雨水は建物の亀裂や隙間から侵入するため、その侵入箇所を防ぐことは応急処置として有効です。
費用は防水テープが500円~1,000円程度、コーキング材は応急処置で使いやすいシリコンタイプが200円~500円程度で、共にホームセンターで購入可能です。
また、コーキングを充填するときはコーキングガンが必要となり、安価なものであれば200円~ホームセンターで購入できます。
雨漏りを起こしている箇所にブルーシートを被せる
屋根や外壁、ベランダ等、雨漏りを起こしている箇所にブルーシートを被せていきましょう。
ブルーシートは水の侵入経路が特定できない場合や広範囲に渡って保護したいときに、簡単に取り付けることが可能です。
ブルーシートは、ホームセンター(DCMグループ、コメリ、カインズ、コーナン、ナフコ、ビバホーム、島忠ホームズなど)に行けば、1.8x1.8mサイズで400円前後で購入できます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
中には隣人や友人の話で「塗装で雨漏りが直ったわ」という話を聞いたことがある人も多いと思います。
たまたま塗装だけで直った運が良かっただけのケースです。
雨漏りの原因が塗装だけでカバーできる単純なクラック(ヒビ割れ)だけだったからですね。
しかし、実際には外壁塗装や屋根塗装だけで解決へとつながらないケースも多々あります。
「塗装すれば直る」と気軽に考えず、正しい原因を知ることで、普段から雨漏りにならないように予防しておきましょう。
その他、雨漏り補修に関するお役立ちコンテンツ

外壁からの雨漏りであれば、コーキングによる応急処置が行えます。あくまでも応急処置なので、専門業者による調査・修理は必要です。ここでは、コーキングを施工するときの流れや注意点などについて説明したします。

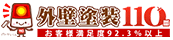



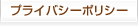


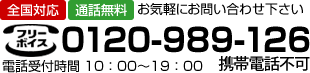





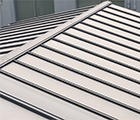












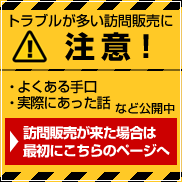

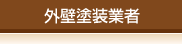
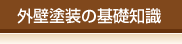
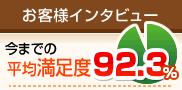
 S 様
S 様 Y 様
Y 様 M 様
M 様 M 様
M 様 S 様
S 様 N 様
N 様 S 様
S 様 M 様
M 様